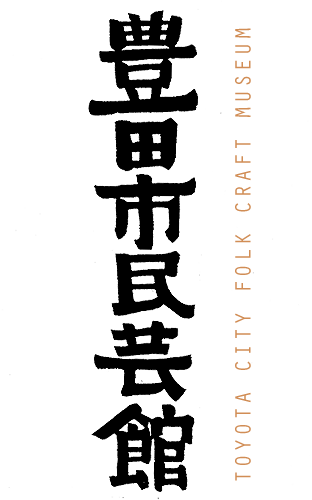年間スケジュール
「或る賞鑑家の眼 -大久保裕司の蒐集品-」
- 開催期間
- 7月13日(土)〜9月23日(月)
- 観 覧 料
- 一般500 円 高大生300 円
<観覧料無料の方>
※要証明、ご本人のみ有効
・豊田市民芸館年間パスポートをお持ちの方
・豊田市内在住で満70歳以上の方
・豊田市内在住の高校生または、豊田市内の高校に通学している方
・豊田市内在住の18歳以下の方(満18歳から最初の3月31日まで)
・豊田市内在住で母子・父子家庭医療費の受給を受けている方
・中学生以下の方
・以下の手帳等の交付を受けている方(ミライロID可)、及びその介添者1名
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・戦傷病者手帳
・療育手帳(名古屋市:愛護手帳)
・日本民藝協会会員本人
・日本博物館協会会員本人と同伴者1名
<100円割引の方>
※要証明、ご本人のみ有効
・豊田市美術館年間パスポートをお持ちの方
・豊田市美術館企画展半券をお持ちの方(有効期間:美術館展覧会チケット記載の会期中)
・日本民藝協会ネット会員の方
・日本民藝館友の会会員の方
・瀬戸民藝館入場券をお持ちの方(有効期間:入場券日付から6カ月以内)
※割引の併用不可
- 会 場
- 第1・2民芸館
古美術・骨董を通じて、青山二郎氏、白洲正子氏、秦秀雄氏等の先達と実際に相見えた数少ない賞鑑家、故大久保裕司氏。その蒐集品は日本の古代から近代までの陶磁器、ガラス、木工、金工、民間仏や小道具、朝鮮時代の諸工芸品から西洋アンティークまで幅広い内容で形成されています。本展ではこの具眼の士が心のままに求め、その元に集まった骨董の品々を紹介します。
写真:蚊遣り豚

「アイヌの美しき手仕事」(日本民藝館巡回展)
- 開催期間
- 10月12日(土)〜12月15日(日)
- 観 覧 料
- 有料
- 会 場
- 第1・2民芸館
日本民藝館創設者の柳宗悦(1889-1961)は、アイヌ民族の工芸文化に早くから着目し、1941年には美術館で最初のアイヌ工芸展となる「アイヌ工藝文化展」を日本民藝館にて開催しました。その際、染色家・芹沢銈介(1895-1984)は、同展の作品選品や展示を任されており、自身もアイヌの手仕事を高く評価し蒐集しました。本展では柳と芹沢の眼によるアイヌ工芸の蒐集品を、日本民藝館と静岡市立芹沢銈介美術館の所蔵品から紹介します。また、当館に近年寄贈された髙松コレクションによるアイヌの工芸品もあわせて展観します。
写真:木綿地切伏刺繍衣裳 19C(日本民藝館蔵)

「民窯 -食のうつわ-」
- 開催期間
- 令和7年1月11日(土)〜4月6日(日)
- 観 覧 料
- 有料
- 会 場
- 第1・2民芸館
「民窯(みんよう)」とは、一般民衆が日々の生活のなかで使う器や道具などを焼く窯、またはそのやきもの自体を指します。民窯という言葉は「民藝」という言葉とともに昭和初期から広く使われるようになりました。今回の展示では、愛知県の瀬戸焼や常滑焼はもちろん、北は岩手県の久慈焼、南は沖縄県の壺屋焼まで、職人の手仕事による食にまつわるやきものを紹介します。
写真:瀬戸本業窯のやきもの

【終了】「美しき手仕事 -新収蔵品を中心に-」
- 開催期間
- 4月9日(火)〜6月30日(日)
- 観 覧 料
- 一般300 円 高大生200 円
<観覧料無料の方>
※要証明、ご本人のみ有効
・豊田市民芸館年間パスポートをお持ちの方
・豊田市内在住で満70歳以上の方
・豊田市内在住の高校生または、豊田市内の高校に通学している方
・豊田市内在住の18歳以下の方(満18歳から最初の3月31日まで)
・豊田市内在住で母子・父子家庭医療費の受給を受けている方
・中学生以下の方
・以下の手帳等の交付を受けている方(ミライロID可)、及びその介添者1名
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・戦傷病者手帳
・療育手帳(名古屋市:愛護手帳)
・日本民藝協会会員本人
・日本博物館協会会員本人と同伴者1名
<100円割引の方>
※要証明、ご本人のみ有効
・豊田市美術館年間パスポートをお持ちの方
・豊田市美術館企画展半券をお持ちの方(有効期間:美術館展覧会チケット記載の会期中)
・日本民藝協会ネット会員の方
・日本民藝館友の会会員の方
・瀬戸民藝館入場券をお持ちの方(有効期間:入場券日付から6カ月以内)
※割引の併用不可
- 会 場
- 第1・2民芸館
本展では、「美しき手仕事」をテーマに、近年収集した作品や寄贈を受けた資料を中心に紹介します。第一民芸館では、日本民藝館展の優品、絞り染めなどの染織品、手漉き和紙やざぜちなどを展示。第二民芸館では、故髙松静男氏が収集したアイヌの工芸品や瀬戸の石皿、そば猪口など、300 点を超える資料の受贈を記念して、多数の優品が含まれた髙松コレクションの中から厳選した作品を紹介します。
写真:胡桃手提げ籠・山葡萄手提げ籠 上村健三